江戸の陶磁器 古伊万里展
会期
2023.06.20〜2023.10.09
展示室
展示室4
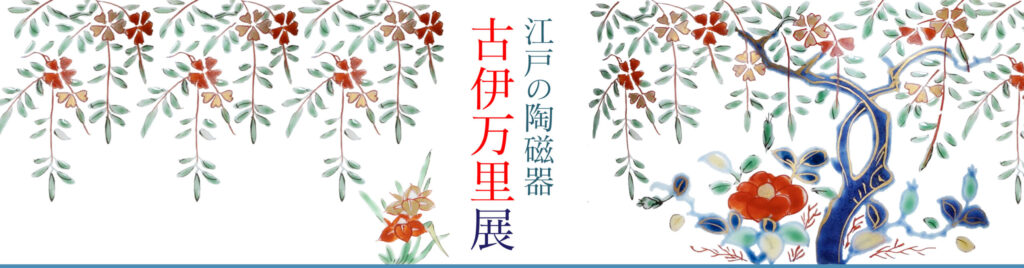
本展会期中に展示する作品情報をデータベースにて公開しております。併せてご覧ください。
江戸時代初期、17世紀の初めに九州 肥前国(現在の佐賀県と壱岐、対馬をのぞいた長崎県)有田で誕生した肥前磁器は、伊万里津(港)から積み出されたことから伊万里焼とよばれるようになりました。なかでも江戸時代の伊万里焼を古伊万里と称しています。
古伊万里は、17世紀半ばから約100年にわたり海外へ盛んに輸出されました。それは、オランダ東インド会社が中国陶磁に代わる品として大量に注文したものでした。
今展では、ヨーロッパの王侯貴族が競ってコレクションし城館を飾った柿右衛門様式や古伊万里金襴手の大型作品とともに、お茶やチョコレートなど新しい喫茶文化を伝える小さなティーポットやカップなども紹介します。
また、大胆な絵付けの古九谷様式の大皿や、鍋島藩窯で特別に作られた色鍋島など、国内向けの江戸時代の陶磁器もあわせてお楽しみください。
古伊万里は、17世紀半ばから約100年にわたり海外へ盛んに輸出されました。それは、オランダ東インド会社が中国陶磁に代わる品として大量に注文したものでした。
今展では、ヨーロッパの王侯貴族が競ってコレクションし城館を飾った柿右衛門様式や古伊万里金襴手の大型作品とともに、お茶やチョコレートなど新しい喫茶文化を伝える小さなティーポットやカップなども紹介します。
また、大胆な絵付けの古九谷様式の大皿や、鍋島藩窯で特別に作られた色鍋島など、国内向けの江戸時代の陶磁器もあわせてお楽しみください。
ヨーロッパに渡った柿右衛門様式と金襴手様式

乳白色の磁肌に清澄な色彩で花鳥や唐人物が絵付けされた「柿右衛門様式」、濃紺の染付に赤と金による桜花や菊など和風な文様が煌びやかな「金襴手様式」は、ヨーロッパの王侯貴族たちを魅了して膨大なコレクションが築かれ、各地の城館に東洋の磁器で部屋中を飾った「磁器の間」が出現しました。

両手のひらにおさまるような小さなポットと高さ5cmほどのカップは、貴重な東洋のお茶を楽しむために日本に注文されたものです。
お茶は、先ず東洋貿易を行っていたポルトガルやオランダに伝わり、1662年、ポルトガルから英国王に嫁いだ王女キャサリンが高価な砂糖を入れて飲む習慣を宮廷にもたらしました。
お茶は、先ず東洋貿易を行っていたポルトガルやオランダに伝わり、1662年、ポルトガルから英国王に嫁いだ王女キャサリンが高価な砂糖を入れて飲む習慣を宮廷にもたらしました。

柿右衛門様式

柿右衛門様式

細身で背の高いカップはチョコレートを飲むためのもの。中南米産のカカオを原料とする新しい飲み物は東洋のお茶とともに、美しい日本の磁器に注がれました。
菱川師宣が描いたような元禄美人たちが青・赤・金の三色のみながら艶やかに描かれています。金襴手様式の「オールド・ジャパン」とよばれるタイプです。
菱川師宣が描いたような元禄美人たちが青・赤・金の三色のみながら艶やかに描かれています。金襴手様式の「オールド・ジャパン」とよばれるタイプです。

国内向けの古九谷様式と鍋島焼
柿右衛門様式 や 金襴手様式 に先立ち、有田で焼かれた「初期色絵」は「古九谷様式」ともよばれ、タイプによって祥瑞手、五彩手、百花手、青手などがあります。大きな皿や鉢の意匠はほぼ一点ものです。古九谷の迫力ある大器は、大名ら富裕層の宴席で注目を浴びたことでしょう。
「鍋島焼」は佐賀鍋島藩直轄の窯で焼かれた磁器で、徳川将軍家への献上、諸大名や公家への贈答、そして藩主の自家用の品として、採算を度外視して生産されました。




